
企業の採用市場は年々競争が激しくなっており、優秀な人材を確保することがますます難しくなっています。ただ求人情報を掲載するだけでは企業の魅力は十分に伝わらず、求職者との適切なマッチングも難しいのが現状です。
そこで、近年多くの企業が注目しているのが「採用ブランディング」です。採用ブランディングとは企業の理念や価値観、働く環境を効果的に伝え、求職者との信頼関係を築くことで、企業に適した人材の応募を増やし、定着率を向上させるマーケティング戦略のことです。
特に、SNSの活用やオウンドメディアとの連携を強化することで、企業の“リアル”な姿を発信し、候補者との接点を増やすことが可能になります。
マーケティング手法とSNS・オウンドメディア運用を組み合わせたPRを得意とする無色透明が、採用ブランディングの目的や重要性、SNSやオウンドメディアを活用した採用ブランディングの成功ポイントを解説します。
【採用✖️ブランディング】企業の「らしさ」を伝え、適切な人材とつながる
企業の採用市場は年々競争が激しくなっており、優秀な人材を確保することがますます難しくなっています。ただ求人情報を掲載するだけでは、企業の魅力が十分に伝わらず、求職者との適切なマッチングも困難なのが現状です。
そこで近年、多くの企業が注目しているのが「採用ブランディング」です。採用ブランディングとは、企業の理念や価値観、働く環境を効果的に伝え、求職者との信頼関係を築くことで、企業に適した人材の応募を増やし、定着率を向上させるマーケティング戦略のことを指します。特に、SNSの活用やオウンドメディアとの連携を強化することで、企業の”リアル”な姿を発信し、候補者との接点を増やすことが可能になります。
マーケティング手法とSNS・オウンドメディア運用を得意とする無色透明が、採用ブランディングの目的や重要性、SNSやオウンドメディアを活用した採用ブランディングの成功ポイントを解説します。
なぜ「採用広報」ではなく「採用ブランディング」なのか
「採用ブランディング」という言葉に似た概念として、「採用広報」があります。これを読んでいる方の中には、「採用広報じゃダメなの?」「採用広報とどう違うの?」と思われる方もいるかもしれません。採用広報と採用ブランディングは混同されやすいですが、目的や手段が大きく異なります。
これまで、多くの企業は求人広告を掲載したり、採用特設ページを開設したり、SNSを活用した情報発信を行う「採用広報」に取り組んできました。しかし、採用広報はあくまで“今ある情報”をもとに一方的に発信する手段であり、求職者に届いたとしても、それが企業の本質的な魅力として伝わるとは限りません。実際に入社してみると、「思っていた雰囲気と違った」といったギャップが生じ、早期離職につながってしまうケースも少なくないのです。
採用ブランディングは、企業の価値観や文化、求める人材像など、求職者にとって重要な情報を整理し、戦略的に伝えていくことで、採用の質を向上させる手法です。企業が求職者と共感を築き、長期的な関係を構築することを目的としています。
採用ブランディングを取り入れることで、企業は単に「応募数を増やす」だけでなく、「企業にマッチする人材を確実に獲得し、定着率を向上させる」ことが可能になります。その結果、企業にとって不可欠な人材を獲得し、育成しながら、組織全体の成長へとつなげることができるのです。
採用ブランディングの成功のポイントとプロセス
採用ブランディングを成功させるためには、適切なステップを踏んで進めることが重要です。以下のポイントを押さえることで、効果的な採用ブランディングが実現できます。
1. 各部署の責任者・担当者でチームを組む
採用ブランディングを進める際には、必ず経営層や各部署からの責任者を集めた「採用ブランディングチーム」を結成します。
実は、「入社後のギャップによる離職」「欲しい人材が獲得できない」といった多くの企業が抱える課題の原因のひとつに、人事部や採用担当のみで採用活動を進めているところにあります。「〇〇部署で人が足りない」という情報だけで、各部署の実情を把握しないまま採用活動を進めてしまうと、現場が求めている人材とは異なる人材を採用するなどのミスマッチが生じます。これは、企業も求職者にとってもとても悲しいことです。
採用活動は人事部だけの仕事ではありません。現場の社員や経営層も関与し、組織全体で採用の目的を共有しながら進めることが求められます。
2.現状の採用の課題・要望を洗い出す
各部署が抱える人材の課題や採用活動の要望を明確にし、人事部や採用担当者と共有します。
「求める人材から応募が来ない」「採用しても定着しない」「他社と差別化ができていない」などの課題があれば、それらを整理し、採用活動の方向性を定めることが必要です。
課題を洗い出し、チームで話し合うことで、求職者に対して適切なアプローチができているか、採用後の定着率を向上させるための施策を行なっているかなど、具体的な課題が明確になり、採用活動だけでなく通常業務での改善点が見つかるなどメリットがたくさんあります。
また、たった1度のMTでは、課題の洗い出しや情報共有ができない場合もあります。採用ブランディングの方向性を決める大切なプロセスなので、2度、3度と回数を重ねて
3. 採用活動のコンセプトを言語化する
採用活動において、自社の特徴を一言で伝えることができるよう、コンセプトを言語化することはとても大切です。言語化することで企業のメッセージが一貫性を持ち、求職者との共感を生み出しやすくなって採用のミスマッチも防ぐことができます。
例えば、以下のような言葉で、明確なコンセプトを作ります。
「私たちは、○○な価値観を持つ人と働きたい」
「私たちは、○○という思いを持って仕事をしています」
「私たちの企業は、○○をすることが使命です」
また、採用コンセプトの言語化は、求職者だけでなく今いる社員に向けたインナーブランディングにも効果的です。採用コンテンツやメッセージに一貫性がある内容を掲げ、発信することで、社内の情報共有・意識統一にもつながります。
採用活動を経営層や人事部のみで行ってしまうと、現場の社員との間に温度差が生じることがあります。採用コンセプトを明確にし、会社全体で共有することで、社員一人ひとりが自社の魅力を理解し採用活動に主体的に関わる環境を作ることができます。結果的に、入社後のギャップを減らし定着率向上にもつながるのです。
3. 採用したい人材のペルソナを設定する
「どんな人材に応募してほしいのか?」を明確にすることが、効果的な採用ブランディングの第一歩です。ペルソナを設定することで、採用活動のメッセージやコンテンツの方向性が定まり、よりターゲットに刺さる情報発信が可能になります。
例えば、以下のような要素を具体的に定めます。
- 年齢層
- 性別
- スキル
- 経験
- 働き方の志向(リモートワーク志向か、チームワーク重視か など)
- 価値観やキャリア志向
4. 最適な情報発信ツールを決める
採用ブランディングでは、どの媒体を活用するかも重要なポイントです。求める人材のターゲット層に合っていないツールを使用すると採用のミスマッチにつながってしまいます。また、SNSやオウンドメディアなど複数のツールを組み合わせた連携体制をとり、継続的な情報発信を行うことも重要です。
【主な情報発信ツールと特徴】
- SNS(Instagram・Twitter・LinkedIn など)
→ 若年層にリーチしやすい。企業の雰囲気やカルチャーをリアルタイムで発信可能 - オウンドメディア(採用サイト・ブログ)
→ 企業の価値観や働く環境を詳細に伝える場として活用。 - YouTube・TikTok(動画コンテンツ)
→ 社員インタビューやオフィスツアーなど、リアルな職場の雰囲気を伝える - 採用イベント・ウェビナー
→ オンライン・オフライン問わず、求職者との直接的なコミュニケーションを図る。
ターゲット層に適したツールを活用することで、効率的に企業の魅力を発信することができる
5. 積極的な情報提供・共有・参加
採用ブランディングは、一度情報を発信したら終わりではなく、継続的に情報を更新し求職者との接点を増やすことが重要です。ポイントは、定期的な情報発信と関係部署とのコミュニケーションです。求職者がリアルタイムで企業の魅力を感じられるように、積極的に情報発信を行うことが成功のカギとなります。
- SNSやオウンドメディアで採用情報や社員の働く様子を継続的に発信
- 新着情報をSNSで発信
- Q&Aセッションやイベントの開催
- SNSのDMやコメントへのレスポンス
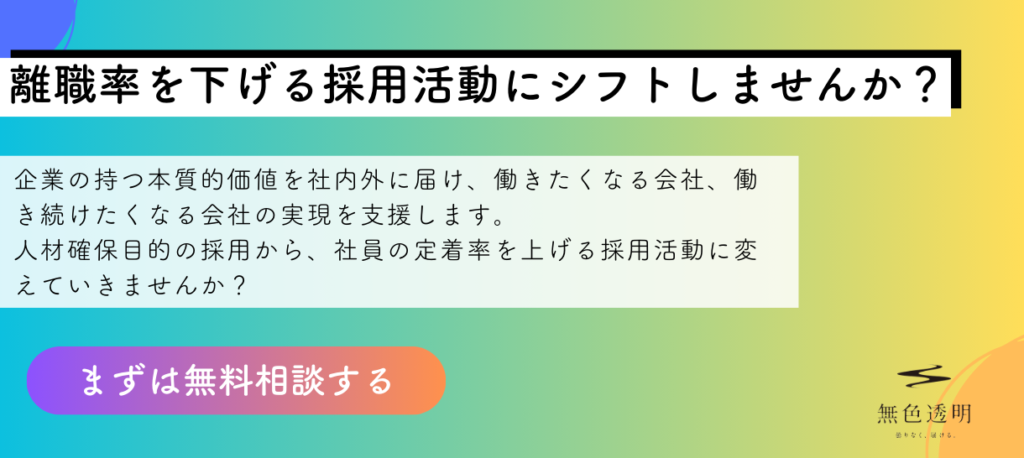
採用ブランディングに活用するツール
① Instagram
Instagramは、視覚的に魅力を伝えやすいSNSとして、多くの企業が採用活動に活用しています。特に若年層の求職者はInstagramを積極的に活用しており、企業の雰囲気を知るための情報源にもなっています。
社員の日常をストーリーズで発信
オフィスの雰囲気や働く社員の姿を日常的に投稿することで、企業のリアルな雰囲気を伝えられる。
「働く人の声」をリール動画で発信
社員インタビューを短い動画でまとめることで、求職者が企業文化を理解しやすくなる。
採用イベントの告知・レポート投稿
説明会やインターンシップ情報を発信し、求職者との接点を増やす。
② Twitter(X)
Twitter(X)は、リアルタイムな情報発信に適しており、短時間で多くの求職者と接点を持つことができます。
社内のちょっとした出来事を発信
「○○部のランチ会」「新しいプロジェクトが始動!」など、親しみやすい投稿を増やす。
社員によるハッシュタグ投稿
「#○○で働く理由」「#新卒採用」など、求職者が検索しやすい形で投稿を工夫する。
求職者とのインタラクション
DMやコメントで求職者からの質問を受け付ける。
③ YouTube・TikTok
最近では、動画コンテンツの活用も進んでいます。YouTubeやTikTokでは、社員インタビューやオフィスツアーを発信し、企業の雰囲気をリアルに伝えることができます。
- 社員の1日ルーティン動画(「1年目社員の1日」「○○部の仕事風景」など)
- 企業のストーリーを伝える動画(創業の背景やビジョン)
- オフィスツアー(「○○のオフィスはこんなところ!」)
④オウンドメディア
オウンドメディア(企業が運営する自社メディア)を活用することで、求職者に対して深い情報を提供できます。SNSは短い情報発信が中心ですが、オウンドメディアでは詳細な情報を伝えられるのがメリットです。
・社員インタビュー記事の掲載
求職者が最も知りたいのは「実際に働く人の声」です。オウンドメディアに社員インタビューを掲載することで、リアルな職場の雰囲気やキャリアパスを伝えることができます。
- 入社のきっかけ:「なぜこの会社を選んだのか?」
- 現在の業務内容:「どのような仕事をしているのか?」
- 働く環境について:「社風やチームの雰囲気は?」
- キャリアの展望:「これからどんなことに挑戦したいか?」
・企業のビジョンやカルチャーを発信
企業のミッションや働く環境を伝えるコンテンツを掲載することで、求職者に「この会社で働きたい」と思ってもらえるようになります。
- 企業の価値観やビジョン:経営層やリーダーからのメッセージを発信。
- 社内イベントや文化:「社内勉強会の様子」「チームビルディング活動」などを紹介。
- 採用情報の詳細:「どんな人材を求めているのか?」を具体的に解説。
・ SNSとの連携
オウンドメディアで発信した記事をSNSでシェアすることで、より多くの求職者に情報を届けられます。例えば、Instagramのストーリーズで「社員インタビュー公開しました!」と告知するなど、各メディアを連携させることが重要です。
まとめ
SNSとオウンドメディアを活用した採用ブランディングは、企業の“リアル”を伝え、求職者の共感を得るための重要な手法です。それぞれの特徴を活かしながら、戦略的に活用することで、採用活動をより効果的に進めることができます。
無色透明では、採用ブランディングの戦略設計からSNS運用、オウンドメディア制作までトータルでサポートしています。採用広報に課題を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。
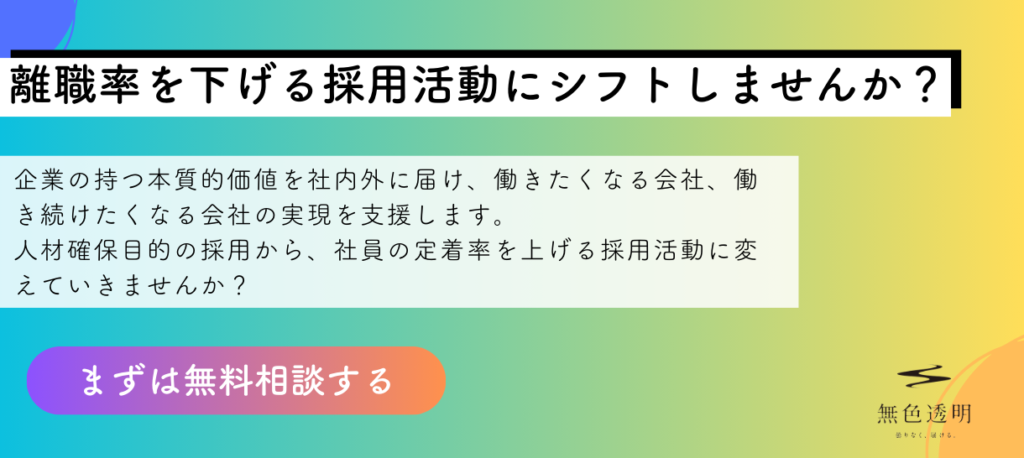

執筆
無色透明 編集部
「川のように流れを作る」のコンセプトのもと、「色づける」「届ける」「循環させる」という3つのステップで企業の本質的価値を高め、最適な形で表現するお手伝いをしています。





