オウンドメディアの支援実績が豊富な無色透明では、企業の採用力向上や離職率低下、社内ブランディング強化を目的としたオウンドメディアも得意としています。
いわゆる『採用オウンドメディア』と呼ばれるものですが、「それって『採用サイト』とはどう違うの?そもそも採用オウンドメディアってなに?」という人も多いかもしれません。また、「そういうのって大手企業がやるものでしょ」「うちみたいな中小企業がやっても意味がないよ」と思っている人も。
今回は、従来の採用サイトと、近年企業が注目している「採用オウンドメディア」の違いや特徴、採用力を向上させるための各ツールの活用方法についてお伝えしたいと思います。
まず押さえておきたい、採用オウンドメディアと採用サイトの定義

採用サイトとは、「今、働きたい人」のための情報窓口
採用サイトは、いわば求人内容を掲載する場所です。仕事内容、勤務地、給与、福利厚生、求める人物像など、いま応募を検討している求職者に向けた、必要な情報を網羅的に掲載することが主な役割です。そのため、構成もある程度決まっており、「会社情報」「募集職種」「エントリーフォーム」といった機能的なコンテンツが中心になります。
最近では、仕事内容や部署の雰囲気を具体的に紹介したり、先輩社員のインタビューを掲載したりと、採用サイトも多様になってきましたが、基本的には求職者に向けた求人票や求人パンフレットと同様の立ち位置です。
採用オウンドメディアとは、「未来の仲間」に向けたブランド価値の発信
求人内容を中心とした情報掲載が目的の採用サイトに対し、「採用」を目的とした自社運営の情報メディアが採用オウンドメディアです。
採用オウンドメディアには、一般的な求人内容は掲載せず、企業文化や取り組み、イベント、商品やサービスの誕生背景、社員一人ひとりに密着したインタビューなど、画像や動画も活用して、よりリアルな情報を掲載します。
「自社らしさ」「社員の想い」「企業文化」などを通して届けることで、“この会社で働いてみたい”という未来の求職者との接点を生みます。
採用サイトと採用オウンドメディア、それぞれの役割と違い
| 採用サイト | 採用オウンドメディア | |
| 主な目的 | 応募の獲得 | ブランドの醸成・興味喚起 |
| ターゲット | 今すぐ働きたい人 | まだ転職を考えていない人 |
| コンテンツ内容 | 募集要項、待遇、選考フロー | 社員インタビュー、企業文化紹介、働き方特集など |
| 更新頻度 | 低(変更があったときのみ) | 中〜高(定期的な情報発信) |
| 表現手法 | テキスト中心、一部動画 | 記事・写真・動画・SNSとの連携 |
両者は競合するものではなく、むしろ「役割分担」がはっきりしているからこそ、併用することでより大きな効果が期待できます。
なぜいま、採用オウンドメディアが注目されているのか?

①情報収集の方法が多様化している
ひと昔前まで、求職者の情報源といえば求人媒体が中心でした。しかし今は、SNSやYouTube、口コミサイト、note、企業ブログなど、あらゆる情報がオンライン上にあふれ、求職者自らが「知りたい情報」にたどり着ける時代になっています。
そんな中で、働く場所を選ぶ基準も大きく変わりつつあります。「給料はいくら?」「休みは取れる?」といった条件面の確認だけでなく、「どんな人がいるのか」「自分はここで楽しめそうか」「居心地のいい環境か」といった“感覚的な納得”を求める声が増えているのです。
だからこそ、採用オウンドメディアには、単に情報を並べるのではなく、「この会社、いいな」「なんだか気になる」と思ってもらえる温度感が求められます。企業の想いや空気感を、自分たちの言葉とビジュアルで丁寧に届けることで、「働いてみたい」と思ってもらえる接点が生まれるのです。
②“待っているだけ”では採用できない時代になった
少子高齢化の影響で、働く人そのものが減っているという現実。「求人を出せば反応がある」という時代は終わり、「どう届け、どう魅せるか」が採用活動の分かれ目になってきています。
企業が“攻め”に転じるうえで、採用オウンドメディアはとても有効です。たとえば、まだ転職を考えていない人に「この会社、なんかいいな」と感じてもらえるきっかけづくり。将来の転職候補者がふと目にしたときに、「ここで働けたら楽しそう」と思ってもらえるような印象を、少しずつ積み重ねていくことが大切です。
つまり、今すぐの応募だけを狙うのではなく、未来の仲間に“働きたい会社”として記憶に残る存在になること。それが、これからの人材戦略には欠かせません。
③「長く働きたくなる会社かどうか」が問われる時代に
求人を出せば一定の応募はある。けれど、いざ採用してみると「こんなはずじゃなかった」と早期離職につながってしまう——そんなケースが後を絶ちません。
いま、多くの企業が「定着率」という視点で採用の質を見直し始めています。単なる条件のマッチングだけでなく、「共感して入社し、やりがいを持って働き続けられるか」。そのためには、会社のありのままを事前に伝えることが不可欠です。
採用オウンドメディアは、企業の価値観や文化、働く人のリアルな声を発信できる貴重な場です。「ここで働くって、こういうことなんだ」としっかり伝えておくことで、入社後のギャップを減らし、長く活躍してくれる人材との出会いにつながります。
採用オウンドメディアを活用するメリットとは?
1. 企業の想いや文化を伝えられる
SNSや外部媒体では、発信の自由度に制限があります。しかし、自社が運営するメディアであれば、フォーマットにとらわれず、伝えたい情報を深く丁寧に発信することができます。
たとえば、「社員が大切にしている価値観」「失敗から学んだリアルなエピソード」「職種を超えた連携の様子」など。これらは一見採用に直結しないように思えて、実は“企業の個性”を求職者に届ける大きな材料になります。
2. 採用コストを中長期的に削減できる
求人広告に毎回費用をかけていた企業も、採用オウンドメディアを育てることで、メディア自体が「資産」として機能するようになります。継続的に運用し、SEO対策などと組み合わせていけば、広告費をかけずに応募が来る状態も夢ではありません。
3. 社員のモチベーションやロイヤリティが上がる
採用オウンドメディアのコンテンツには、社員が登場することが多くあります。社員インタビューや現場のストーリーを発信する過程で、働く人自身が「自分の仕事の意味」や「会社への想い」に改めて気づく機会になることも。
その結果、社内のエンゲージメントが高まり、インナーブランディングにもつながります。
採用サイトだけで十分」と考えている企業へ
採用活動に本腰を入れたいと考えたとき、「とりあえず採用サイトを作って情報を載せておけばいい」と思っていませんか?
確かに、求人情報や募集職種などを網羅的に掲載する採用サイトは、必要なツールのひとつです。しかし、求職者の価値観が多様化し、情報収集の手段も広がっているいま、求められているのは“情報を伝えるだけの場所”ではありません。これからの時代に必要なのは、「この会社で働いてみたい」と思ってもらえるような情報の届け方。
つまり、応募を促すよりも先に、興味を引き、共感を育て、“好きになってもらう”ことが、採用活動の第一歩なのです。そう考えたとき、企業の人や文化、ストーリーを軸に発信できる採用オウンドメディアは、大きな力を発揮します。
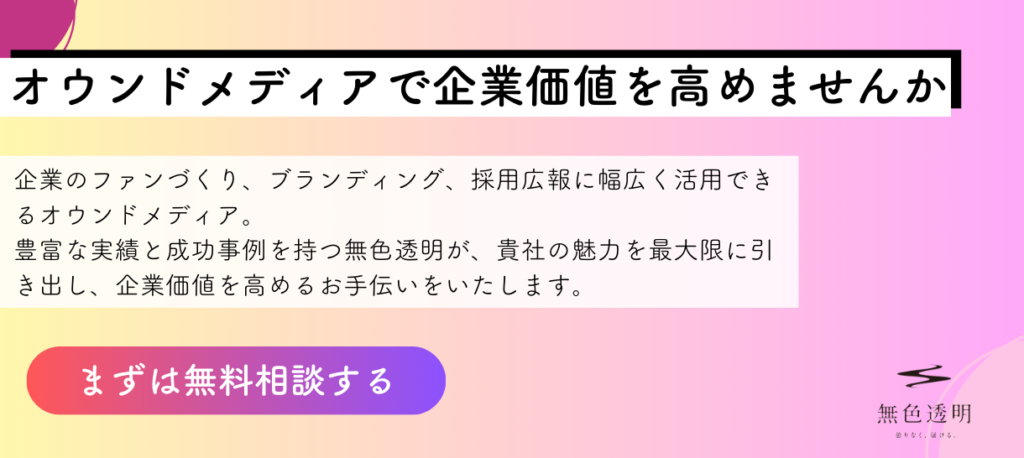
「共感」からはじまる採用活動へ
採用サイトと採用オウンドメディアは、どちらか一方で完結するものではありません。それぞれ異なる役割を担いながら、組み合わせることで、より豊かな採用体験をつくることができます。採用オウンドメディアを活用することで、企業は「誰を、どんな想いで迎え入れたいのか」を自らの言葉で伝えることができるようになります。
それは、ただの情報提供ではなく、「共感」から始まる採用活動へのシフト。企業の想いに惹かれた人と出会い、応募につなげていく——そんな新しいスタイルの採用活動が、いま求められているのです。

執筆
無色透明 編集部
「川のように流れを作る」のコンセプトのもと、「色づける」「届ける」「循環させる」という3つのステップで企業の本質的価値を高め、最適な形で表現するお手伝いをしています。





